歯ぎしり、顎関節症
南森町天神橋歯科の
歯ぎしり・顎関節症の治療

歯ぎしり、顎関節症に精通した
ドクターが在籍
当院長は、大阪大学 大学院にて顎関節症や歯ぎしりなどの研究に携わり歯学博士号を取得した歯科医師です。
豊富な知識と経験をもとに適切な診査・診断を行い、患者さまに合わせた治療や予防方法をご提案しております。奥歯やあご周りに違和感が続くなど、少しでも気になる症状がありましたら一度当院へご相談ください。
顎関節症(がくかんせつしょう)とは
耳の前方にある関節を、顎関節(がくかんせつ)と呼びます。顎関節症は何らかの原因により、顎関節周りに痛みを生じたり、口が開かないなどの機能障害が起きている状態です。
顎関節症の原因は患者さまによって異なりますが、精神的ストレスから歯ぎしりや食いしばりをするようになり、顎関節や顎の筋肉に負担を蓄積してしまうことで発症することも多くあります。
近年では、日本人の2人に1人が顎関節症を経験するとも言われており、とても身近な病気となってきています。
顎関節症セルフチェック
- 口を開けて指が縦に3本入らない
- ︎食事をすると耳の付け根や
こめかみが痛む - 起床時に顎の周りに疲労感や
違和感がある - ︎口を開け閉めすると音がする
(カクカク等) - 慢性的な肩こり、頭痛、耳鳴りで
悩んでいる など
上記のような症状は顎関節症によるケースがあります。
顎関節症は、ストレスや生活習慣、噛み合わせや外傷の既往など、様々な要因によって引き起こされる可能性があるため、まず原因を究明することが重要です。
顎関節症の分類
Ⅰ型:咀嚼筋痛障害
咀嚼筋(顎を動かす筋肉)における障害です。症状としては 筋肉痛のようなものもあります。
Ⅱ型:顎関節痛障害
顎の関節に痛みを伴う障害です。顎関節の骨と骨の間にある関節円板を支える組織や、関節包・靭帯という部分に何かしらの問題が起こり痛みを生じます。
Ⅲ型:顎関節円板障害
顎関節の内部構造の動きやずれを主体とする障害です。「a: 復位性」と「b: 非復位性」の2つのタイプに分けられます。
aタイプでは口を開け閉めするときに音がする場合が多く、bタイプでは口を開こうとしたときに途中で引っかかりがあるといった特徴が見られます。
関節円板のずれを伴う人は、無自覚の人を含めると人工の3分の1程度存在するとも言われています。
Ⅳ型:変形性関節症
顎関節の骨の変形によって生じる痛みや運動障害です。 このケースでは関節を元の状態に戻すことは難しく、できる限り症状を取り除くことで運動機能を回復させることが主な治療となります。症状に応じて手術が必要なケースもあります。
顎関節症の治療法
について
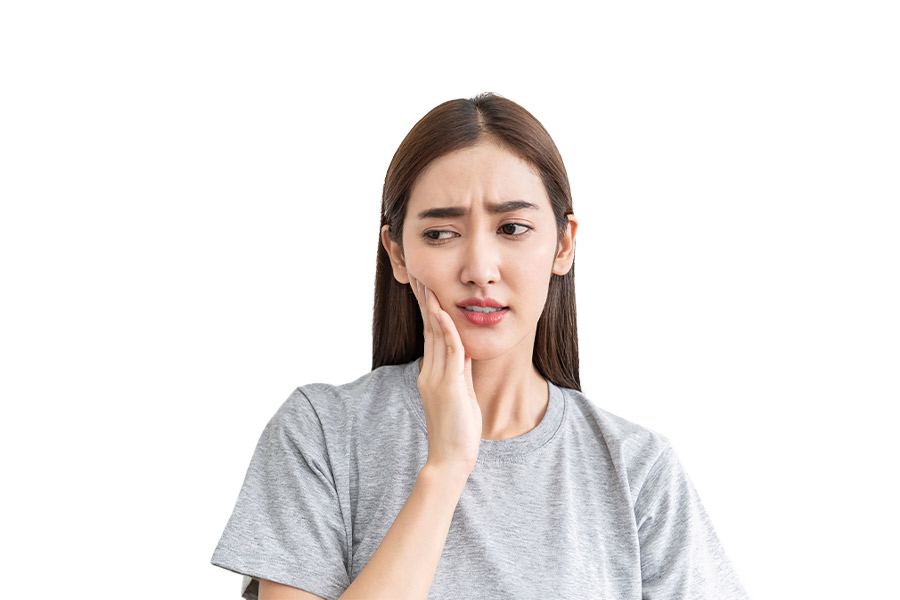
顎関節症は生活習慣病的な部分が大きいため、改善するためには原因となる悪習癖を取り除くセルフケアを、患者さまご自身に実践していただくことが中心となります。
また症状に応じて、原因となる噛み合せの矯正、薬物療法、関節腔内の洗浄、内視鏡下での外科的手術などの治療を行なう場合もあります。
それぞれの症状やお口の状態に合わせて、的確な診査・診断の上、適切な治療をご提供いたします。
顎関節症の治療法
マウスピース治療
顎関節症は噛み合わせや顎の位置異常から起こるものが多いので、正しい顎の位置に誘導してくれるマウスピースを夜寝るときに装着し、顎関節の安静化を図る方法です。
現在の顎関節治療の第一選択になることが多い方法です。

生活習慣の改善
日頃の生活習慣を振り返り、顎に負担をかけている行為を見直すことで改善を図ります。

物理療法
マッサージや熱、電気を用いて、顎関節の血流を増加させ、老廃物を代謝したり、腫れや痛み、ストレスを軽減させることで顎関節症の改善を図ります。

運動療法
顎関節を動かす体操を、医師と一緒または患者さま自身が行い関節の動きをよくする方法です。
動かし方にはコツがあり、無理やり行うとかえって逆効果になりますので、必ず医師の指導のもと行うようにしましょう。

薬物療法
消炎鎮痛薬によって、痛みと炎症を抑えます。

正しい噛み合わせを整える治療
歯並びや噛み合わせが顎関節症を引き起こしている場合、上記に挙げた方法では根本的には解決することができません。
歯列矯正治療や、詰め物・被せ物の入れ替え、インプラント治療などによって正しい噛み合わせを整えることで、顎関節症の原因である不正咬合を治療する方法です。
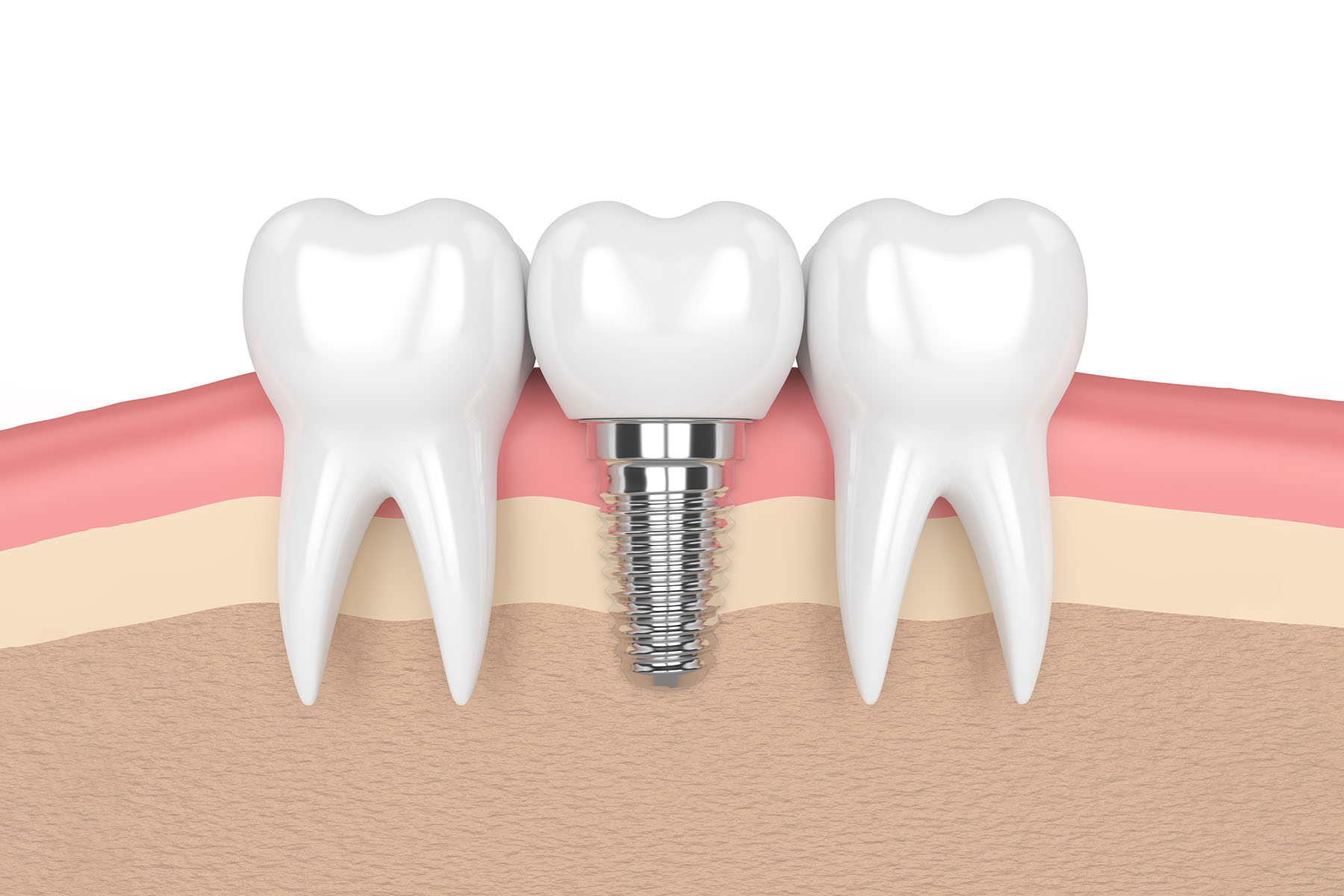
外科治療
非常に稀ですが、以上の方法でも改善がない場合は、関節の中を洗浄したりする外科処置を行う場合があります。




